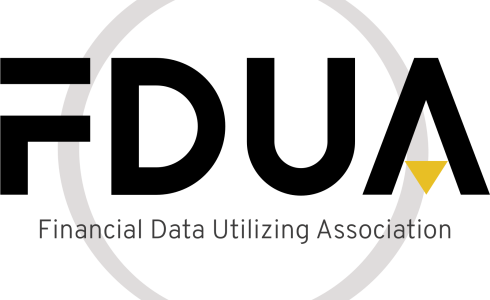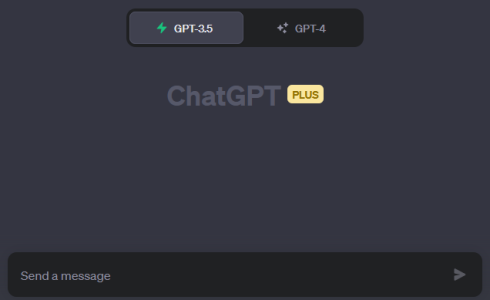なぜ就職活動において企業と就活生の間にミスマッチが起きるのか?
工学系研究科 川島涼輔
1. はじめに
アメリカの就職事情をデータで読み解く:学生と企業のギャップとは?
アメリカではここ数年、若い世代を中心に「就職が難しい」という声が強まっています。背景には、経済の不安定さや関税政策の影響があるといわれていますが、注目すべきは STEM(科学・技術・工学・数学)系の専攻でさえ失業率が高いという点です。たとえば、コンピューターサイエンスや物理といった分野の学生でも、思うように仕事に就けないケースが増えているのです。
では、なぜこんなことが起きているのでしょうか?
「経験5年以上」の壁
よく耳にするのが、企業が「最低でも5年の実務経験」を求めるケースです。まだ大学を出たばかりの若者にとって、これはかなり高いハードルですよね。私自身も求人情報を見ていて、こうした条件をしばしば目にしました。果たしてこれは一部の企業だけなのか、それとも広く見られる傾向なのか?——そんな疑問から、今回データを使った分析を行いました。
学生と企業、2つのデータを比べてみた
今回調べたのは、学生と企業、それぞれの視点を表す2つのデータです。
- 学生側のデータ:履歴書(レジュメ)の内容を集めたもの。学生がどんなスキルや知識をアピールしているのかがわかります。近年ではAIを使って履歴書を自動でふるい分けする仕組みが増えていて、このデータもその研究目的で作られたものです。
- 企業側のデータ:求人サイト「Monster.com」から集められた求人情報。仕事内容や必要なスキル、給与、業界などの情報が載っており、企業がどんな人材を求めているのかを読み解くのに役立ちます。
この2つを照らし合わせることで、「学生がアピールする力」と「企業が求める条件」の間にどんなズレがあるのかを見ていこうというわけです。
研究の目的
今回の分析のゴールはシンプルです。
- 本当に学生と企業の間にミスマッチはあるのか?
- あるとすれば、それはどんなギャップなのか?
たとえば「企業は経験を求めすぎているのか」、あるいは「学生のスキルが足りていないのか」。その答えをデータから探っていきたいと考えています。
- 研究の手法と結果
学生と企業でズレる「言葉の使い方」:就活データ分析から見えたこと
就職活動をしていると、履歴書にどんな言葉を書けばいいのか、また企業は求人票でどんな言葉を使っているのか、気になる方も多いと思います。今回の研究では、学生の履歴書と企業の求人票を比べて「どんな言葉がよく使われているか」を調べてみました。
研究でわかった3つのポイント
調査では、次の3つの観点から語彙の違いを分析しました。
- 学生はよく使うけど、企業ではあまり見かけない言葉
- 企業ではよく使うけど、学生の履歴書にはあまり出てこない言葉
- 両方で使われるけど、使う頻度に差がある言葉
特に「経験年数」に注目し、学生と企業がどんな表現をしているかを詳しく分析しました。
履歴書と求人票を比べてみた:ワードクラウドで見えること
みなさんは「ワードクラウド」をご存じでしょうか?
文章に出てくる言葉を数えて、たくさん出てくるものほど大きな文字で表示する図のことです。よくSNSなどでも見かけると思います。今回は、このワードクラウドを使って「学生の履歴書」と「企業の求人票」に書かれている言葉の違いを調べてみました。
学生と企業、それぞれが強調する言葉
まずは履歴書に多い言葉をワードクラウドにしてみました。そこには学生が自分をアピールするときによく使う言葉が大きく出てきます。一方で、求人票を同じように可視化すると、企業が求めるスキルや条件が目立ちます。
このように左右に並べて比べると、「学生はこう書くけど、企業はこう表現するんだ」という違いが直感的にわかります。
さらに、頻出する上位の言葉をランキングにしてみると、両者の“言葉のクセ”がより鮮明になります。履歴書では「挑戦」「努力」といった自己表現が多く、求人票では「経験」「スキル」といった条件的な言葉がよく登場しました。

「経験年数」に見るギャップ
もうひとつ注目したのは、「経験年数」に関する表現です。
履歴書には「2年経験」「半年インターン」など、学生が自分の経験を数字で書いています。求人票では「3年以上の経験」「5年以上の実務経験」など、企業が求める具体的な年数が記載されています。

履歴書と求人票、どれくらい「言葉」が似ている?
就職活動では、学生の履歴書と企業の求人票を比べることがよくありますよね。でも実際のところ、「使っている言葉」はどれくらい似ているのでしょうか?
今回は、その“言葉の似ている度合い”を数値で測ってみました。
コサイン類似度ってなに?
使ったのは「コサイン類似度」という方法です。難しそうに聞こえるかもしれませんが、ざっくり言うと 「2つの文章がどれくらい似ているかを0~1の間の数で表す」 ものです。
- 1に近い → ほぼ同じ言葉づかい
- 0に近い → ほとんど違う言葉づかい
というイメージです。
結果はどうだった?
学生の履歴書と企業の求人票を比べたところ、「0.56」という数値になりました。
これは 半分くらいは似ているけれど、まだまだ違いも大きい という結果です。
たとえば、履歴書には「挑戦」「努力」といった自己PR的な言葉が多く見られるのに対し、求人票には「経験」「スキル」といった条件的な言葉が目立ちます。この“表現のずれ”が数値としても表れているのです。
学生と企業が求める「経験年数」の違いを見える化してみた
履歴書や求人票には「経験〇年」といった表現がよく出てきますよね。では実際に、学生が書く経験年数と企業が求人票で求める経験年数は、どのくらい違うのでしょうか?
今回は、それをグラフにして比べてみました。
棒グラフで比べる「経験年数」
まず、履歴書と求人票から「経験年数」に関する記述だけを取り出し、それを棒グラフ(ヒストグラム)にしました。
- 左側:学生が履歴書に書いた経験年数
- 右側:企業が求人票に記した経験年数
こうして並べてみると、学生は「1年未満」や「数か月」といった短い経験を書いていることが多いのに対し、企業は「3年以上」「5年以上」など、より長い経験を条件にする傾向があることがわかりました。

データをきれいに整える工夫
ただし、この「経験年数」のデータには課題がありました。学生の経験は短く偏りがちで、企業の条件は長めに集中しているため、そのままではグラフの形がいびつになってしまいます。
そこで次のような処理をしました:
- 年数をすべて「月数」に変換(例:1年 → 12か月)
- 全部に1か月を足して、0が出ないように調整
- 対数(log)を取って、極端な差をならす
こうすると、データのばらつきを残しつつも、履歴書と求人票の違いがより比較しやすくなります。

見えてきた結果
処理をしたデータをもとに分布を比べたところ、面白い傾向が見えてきました。
- 履歴書:学生が書く経験年数の多くは短め
- 求人票:そのピークは、履歴書のピークよりもおよそ 2〜3倍長い経験 のところにあった
つまり、企業は新卒や若手に対しても、実際に学生が持っている経験より「2〜3倍多い経験」を条件として出している傾向があるのです。
3.考察
思ったより似ていた!履歴書と求人票の言葉
分析してみると、履歴書と求人票の両方に共通してよく出てくる言葉がありました。たとえば 「experience(経験)」 や 「skill(スキル)」。企業のほうが「experience」をより頻繁に使う傾向はありましたが、両者で大きな差があるわけではなかったのです。
さらに 「team」や「management」 という言葉も両方で多く使われていました。これはアメリカの労働市場において、チームでのマネジメントやリーダーシップ経験が重視されていることを表していると言えそうです。
全体としての「言葉の似ている度合い」を測ると 0.57(1に近いほど似ている)という数値に。これは、学生が履歴書を書くときに「企業に伝わりやすい言葉」をある程度意識している可能性を示しています。
違いもあった!学生と企業の視点
もちろん、違いもはっきり出ました。
- 学生側では「project」という言葉が多く使われていました。これは、自分の取り組みや実績をアピールしたい気持ちの表れだと考えられます。
- 企業側では「customer」「service」「ability」といった言葉が目立ちました。これは「顧客にサービスを提供できる即戦力」を求める姿勢を示しているといえるでしょう。
「経験年数」に見る大きなギャップ
さらに「経験年数」に注目すると、もっとはっきりした違いが見えました。
- 学生の履歴書では 「month(月)」 という表現が多く、特に「1年」がよく出てきます。
- 企業の求人票では 「year(年)」 が多く、特に「5年」が頻繁に登場しました。
つまり、学生は「数か月〜1年程度の経験」を書く一方で、企業は「5年以上の経験」を求めることが多いのです。
これは筆者が日頃LinkedInで感じていた「企業の要求は高め」という印象とも一致していて、データでも裏付けられる結果となりました。
4.終わりに
この研究の限界とこれからの展望
今回の研究から、学生と企業の間にある「経験年数のギャップ」が見えてきましたが、もちろんいくつかの限界もあります。
この研究の限界
- アメリカ限定の分析
今回の調査はアメリカの求人市場を対象にしているため、日本や他の国にはそのまま当てはまらない可能性があります。 - 言葉の文脈までは見ていない
使われた言葉を数えて比較しましたが、その言葉がどんな意味で使われているかまでは考慮していません。例えば「project」という言葉も、学生にとっては学内課題を意味することが多いですが、企業にとっては大規模な顧客案件を指すことがあります。こうした文脈の違いは、今回の分析では拾えていません。
今後の展望
今後は、より高度な技術を使って分析を進めていきたいと考えています。特に注目しているのは、大規模言語モデル(LLM) や 意味ベクトル(semantic embeddings) といった技術です。これを活用すれば、単純に「同じ言葉が出たかどうか」ではなく、その言葉が どんな意味合いで、どんな感情や背景とともに使われているのか を深く理解できるようになります。
また、この研究手法は就職活動だけでなく、他の分野にも応用できる可能性があります。
- 婚活における男女の価値観のズレ
- 消費者と企業のニーズの食い違い
こうした“社会の中のミスマッチ”も、言葉を分析することで見える化できるかもしれません。
まとめ
今回の研究はまだ第一歩に過ぎませんが、学生と企業の「経験年数のギャップ」を数値で示すことで、就職活動におけるミスマッチの一因を明らかにできました。
今後は、言葉の意味や使われ方の違いまで掘り下げることで、より本質的なマッチングの改善につながるはずです。このアプローチが、就活に限らずさまざまな場面で「すれ違い」をなくすヒントになることを期待しています。
アワード一覧
- スーパーデータサイエンスアワード2025年度春学期
- スーパーデータサイエンスアワード2024年度秋学期
- スーパーデータサイエンスアワード2024年度春学期
- スーパーデータサイエンスアワード2023年度秋学期
- スーパーデータサイエンスアワード2023年度春学期